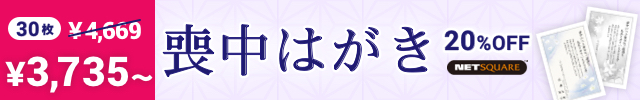<<第14回:【必要に応じて】お墓を承継するには【お墓の承継手続き・永代供養墓・墓じまい】
ここが大切!
- 改葬の前に新しいお墓の手配をする。
- 改葬の事情を菩提寺にきちんと説明する。
- 改葬許可申請書を手配する。
お墓の引っ越しの理由はさまざま
お墓や遺骨を移動して供養したいと考える人が増えています。お墓の場所や遺骨を新しいお墓に移すことを改葬(かいそう)といいます。つまり、お墓の引っ越しです。
その理由は、郷里にあるお墓が遠くてお参りできない、お墓の近くに維持管理する人がいなくなった、お墓の場所が山の上にあり、水やお花を持って上がるのが大変になった、父方・母方のお墓を1つにして両家墓(りょうけぼ)にしたい(お墓の管理も楽になる)、お墓の老朽化など、さまざまです。特に多いのが親の実家近くにあるお墓を子の家の近くに移すというケースです。
改葬には、①遺骨だけを移す、②遺骨と墓石を移す③骨壺などの中から分骨する、などの方法があります。
改葬の手続きと新しい墓の開眼供養・納骨
改葬に当たっては、改葬の事情を寺院や霊園にきちんと説明し、理解を求める必要があります。特にお墓のある寺院にとっては、改葬は「檀家が離れる」ことになるため、快く思わないこともあります。説明のときには、今までの感謝の気持ちも伝えるようにしましょう。
改葬に際しての手続きは以下のようになります。改葬の申請人は、墓地の使用者(お墓の使用権利を持っている人)または墓地の使用者から委任を受けた人となります。申請人の印鑑は実印である必要はありません。
①新しい墓地を確保し、新しい墓を建て、永代使用料と管理料を納め、永代使用許可証(受入証明書)を発行してもらう。

②既存のお墓がある寺院や霊園から改葬の許可を得る。
③既存のお墓がある市区町村役場で改葬許可申請書をもらい、それに必要事項を記入する。既存のお墓の菩提寺や霊園の管理者、改葬先の墓地管理者の署名・押印も必要。
④③の改葬許可申請書と、改葬先で発行してもらった永代使用許可証(受入証明書)を既存のお墓のある市区町村役場に提出し、役場から改葬許可証を交付してもらう。
⑤既存のお墓で閉眼供養(御霊抜き法要)をして、遺骨を取り出す。
⑥既存のお墓の解体・撤去工事をして、更地に戻す。
⑦改葬先の墓地管理者に④の改葬許可証と永代使用許可証(受入証明書)を提出し、納骨の日時を決める
⑧納骨の日、新しいお墓で開眼供養を行い、納骨する。
檀家をやめるときに菩提寺に離檀料を払う必要は?
長い付き合いのある菩提寺(先祖代々の墓を供養してくれる寺院)からお墓を移動させるとき、よく起きるトラブルが菩提寺から離檀料(りだんりょう)を請求されることです。
しかし、永代使用料や管理料を支払っているのですから、本来は払う必要はありません。
改葬にかかる費用は、既存のお墓の墓石を撤去して、そこを更地(さらち)にする費用と、新しいお墓の購入・建立の費用だけです。
改葬の手続きの流れ
- 新しい墓地を確保する【新しい墓を建て、使用料と管理料を納め永代使用許可証(受入証明書)を発行してもらう】
- 既存のお墓の菩提寺に承諾を得る【今までの感謝の気持ちを伝えよう。離檀料を払う必要はない】
- 改葬許可申請書に記入する【既存のお墓がある市区町村役場で改葬許可申請書をもらい、それに必要事項を記入する。既存のお墓の菩提寺や霊園の管理者、改葬先の墓地管理者の署名・押印も必要。】
- 改葬許可申請書の提出、改葬許可証の交付【改葬先で発行してもらった永代使用許可証(受入証明書)を既存のお墓のある市区町村役場に提出し、役場から改葬許可証を交付してもらう。】
- 閉眼法要【既存のお墓で閉眼供養(御魂抜き法要)をして、遺骨を取り出す】
- 既存のお墓の撤去【既存のお墓の撤去・解体工事をして、更地に戻す】
- 改葬許可証の提出【改葬先の墓地管理者に④の改葬許可証と永代使用許可証(受入証明書)を提出し、納骨の日時を決める】
- 開眼供養・納骨【納骨の日、新しいお墓で開眼供養を行い、納骨をする】
お墓を閉じるときは閉眼供養をし、新しくお墓を建てたときは開眼供養をする
お墓を改葬するときや、新しく造り直すとき、既存のお墓を撤去する前に行わなければいけないのが閉眼供養です。御魂抜き(みたまぬき)ともいいます。墓石から魂を抜いて、ただの石に戻す儀式です。
その逆で、新しいお墓が完成したら、まず開眼供養(開眼式)を行います。御魂入れ(みたまいれ)、入魂式ともいいます。僧侶の読経(どきょう)によってお墓に魂を入れてもらう儀式です。お墓は建てただけではただの石にすぎず、この儀式をして初めて礼拝の対象になるのです。僧侶にはお布施とお車代を包みます。
改葬許可申請書の記入例

改葬許可申請書 見本